取材・文:浅見聖怜奈
最優秀指導者賞インタビュー | コラム&インタビュー
鈴木 恒太
鈴木恒太先生は、本協会主催の「第3回全日本こどもの歌コンクール」重唱・合唱部門にて『最優秀指導者賞』をご受賞されました。
八王子市立第一小学校の音楽専科の教諭として、合唱団のご指導をされていらっしゃいます。
常に謙虚で、勉強熱心、音楽に真摯に向き合う先生のこれまでの歩みについて、また子どもたちとの対話を大切にされていらっしゃる合唱団のご指導について、具体的にお伺いさせていただきました。
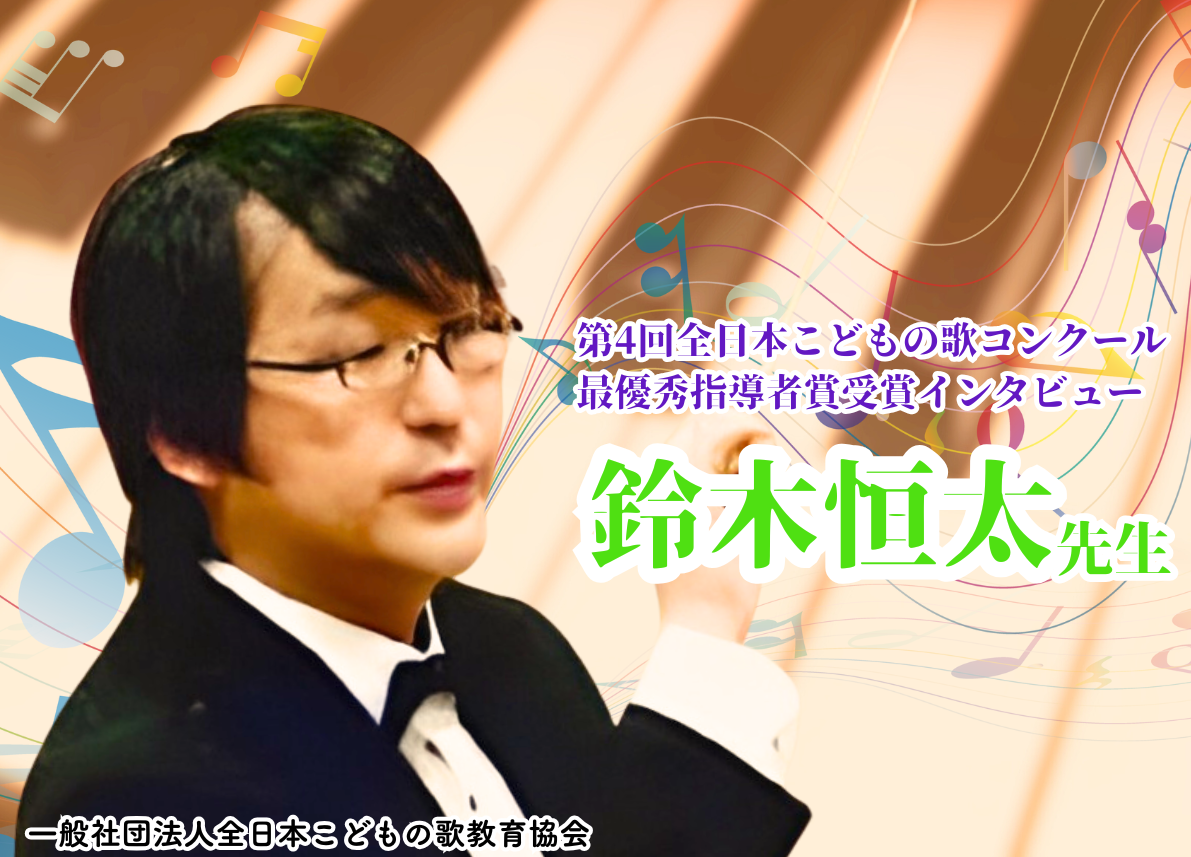
- 鈴木恒太(すずきこうた)
千葉県千葉市出身。千葉大学大学院音楽教育専攻を修了。
千葉市立幸町第三小学校在学時に、生涯の恩師となる田川伸一郎先生と出会い、吹奏楽部に所属。
恩師のような音楽教師の道に憧れて小学校教師になるが、約10年間の学級担任を経て、ようやく音楽専科に転科。
前任校の青梅市立第三小学校で音楽専科及び初めてのバンド顧問として6年間指導し、同バンドを東日本学校吹奏楽大会、日本管楽合奏コンテスト全国大会・最優秀賞、全日本金管バンド選手権本選考会・全国第二位に導いた。青梅市教育委員会表彰、青梅市芸術文化奨励賞を受賞。
昨年度から、40年以上の歴史がある合唱団のある八王子市立第一小学校に赴任し、2年目で、NHK全国学校音楽コンクール都大会本選出場、TBSこども音楽コンクール重唱部門優秀賞、第3回全日本こどもの歌コンクール全国大会・金賞・グランプリを受賞。
やればできる本校の子どもたちと共に目標をもって活動を続けている。
―鈴木先生の音楽との出会いについて教えてください。
私の音楽との出会いは、小学3年生の時に恩師に誘っていただき吹奏楽部に入ったことです。
大きな声では言えませんが、それまでの私はどちらかというと音楽は好きな方ではなく、成績も、本当に子どもたちには言えないくらいでした…。
しかし、吹奏楽部に誘ってくださった恩師・田川伸一郎先生との出会い、そして吹奏楽との出会いが、これまで音楽が好きとは言えなかった(大嫌いだった)私を、音楽が大好きで今では音楽を教える先生をするまで大きく変えてくれました。
好きではないものが、勉強をすることで好きに変わったというこの僕自身の経験は、子どもたちと出会った時にいつもお話しています。
田川伸一郎先生は、千葉県の小学校教諭(音楽)として着任した全ての学校を計14回、全国1位に導かれました。教員をご退職されたあとは、バンド指導や音楽教育のサポートをして北海道から沖縄まで全国各地を駆け回り、ご活躍されていらっしゃいます。
―吹奏楽がきっかけだったのですね。ちなみに、何の楽器をご担当されていたのですか?
はい。トランペットを担当していました。小学校・中学校と吹奏楽に打ち込み、高校では千葉県少年少女オーケストラに第1期生として所属し、音楽に没頭しました。
当時小学校では、歌って踊れるバンドを目指しており、そこで歌う機会をいただいたりして、合唱にもふれました。
―少年時代は音楽に没頭されていた鈴木先生ですが、いつ頃音楽の先生を目指そうと思ったのですか?
そうですね。中学生くらいの時には漠然と音楽の先生になりたいな、という気持ちが芽生えていました。というのも、小学校時代の恩師の田川先生の影響が大きく、先生のような音楽教師になりたいと憧れていましたね。
東京都の小学校教諭になってからしばらくは担任をしており、念願の音楽専科の教諭になるまで10年くらいかかりました。今やっと専科になって9年くらいたったところでしょうか。
―そんな鈴木先生がご指導をされていらっしゃいます、八王子市立第一小学校合唱団について教えてください。
私自身が長年吹奏楽に親しんできたこともあり、前任校(青梅市立第三小学校)では6年間金管バンド部の指導をしていました。
それが昨年度、突然合唱団の歴史が長い八王子市立第一小学校に赴任が決まりました。最初は合唱部の指導など未経験の私はどうしたらよいかと頭を悩ませましたが、試行錯誤を繰り返しながら子どもたちと歩み、今年で2年目を迎えます。
本校合唱団は例年当たり前のようにNHKの合唱コンクールに参加していたようなのですが、赴任当初、なぜコンクールに出るのか、その気持ちが団員の中で少しバラバラなように見受けられました。そこで今年は楽しく合唱に親しむ「歌広場コース」とその上でコンクールへの出場を目指す「コンクールコース」の2つのコースを作ることにしました。
合唱団には4〜6年生の約35人が所属しており、学校の音楽会や地域の行事など、全団員で取り組む場面もたくさんありますが、コンクールに関しては、挑戦したいという想いを持った子どもたちで都度メンバーを編成し取り組んでいます。
楽しく歌いたいという想いと、コンクールでさらに質の高い合唱をつくりあげたいという想いがぶつかり合ってしまうと練習への取り組み方など、なかなか難しいように感じました。そのような経緯もあり、今回のコンクールは「八王子市立第一小学校合唱団・五重唱」として本人とご家庭で納得して出場を希望した5人での出場となりました。
―そんな選抜メンバーで挑戦された第3回全日本こどもの歌コンクール重唱・合唱部門では見事グランプリ・金賞、ベヒシュタイン賞、審査員長賞、聴衆賞をご受賞されましたが、鈴木先生はコンクールに出場することの意義をどのようにお考えでいらっしゃいますか?
そうですね。コンクールに出ることは、決して当たり前のことではないと思っています。特に本校は合唱団として、コンクールに長年出続けている歴史があるので、出場できるのは本当はありがたいことなんだという気持ちをもってほしいと思います。
今回も、どうしてコンクールに参加するのか、したいのか、子どもたちによく問いかけましたね。
もちろん賞を目指して努力することはもちろんですが、何のためなのか、それを子どもたちに問いかけ、考えてもらう時間を大切にしています。
このように子どもたち自身に考えてもらうと参加する目的が明確になっていきます。
今回のコンクールに向けては、「1回しかない小学校の夏休みをダラダラ過ごすのではなく、全力で仲間とともに目標に向かって取り組みたい」と、本来の目的を子どもたち自身が見つけ、言葉にできるようになりました。その気持ちが共有できていたら、参加することに意味があると思えるので、一緒に頑張ろうと話し合いをしましたね。
合唱団が長年挑戦していたというNコンについては、人数が少なくなったので、私は今年は出場をやめようと子供たちに話していましたが、この全日本こどもの歌コンクールで受賞させていただいたことによって自信がついたのか、人数的に圧倒的に不利でも、「恥をかいてでも挑戦してみたい」という子どもたちの気持ちを聞いて、「それなら先生も一緒に恥をかくよ」と出場を決めました。
その結果、たまたま本校の合唱団としては26年ぶりの金賞・予選突破の結果をいただくことができ、東京都本選に出場させていただきました。
十分すぎる結果をいただいて感謝していますし、子どもたちにはそういった本来の目的を忘れずにこの先も歩んでいってほしいと思っています。
コンクールに参加する時、賞だけを目的にすると、思うような結果が得られなかった時、「参加しなければよかった」となってしまいます。しかし、たとえ目標にしていた賞に届かなかったとしても、目的がはっきりとしていれば「参加してよかった。よい経験になった」と感謝の気持ちが芽生えるのではないでしょうか。
仲間とともに頑張った思い出は一生の思い出です。うまくいかなかったことも含め、大人になった時に笑って振り返ることができたらすてきだなと思います。

―常に子どもたちに問いかけ、子どもたち自身が考え、一緒に歩まれる姿勢はとても素敵ですね。その先生が大切にされていらっしゃるミーティング、また日頃の練習への取り組みについて教えてください。
そうですね。子どもたちの練習の様子を見ていると、時々違和感を感じる時があります。それは、何のためにやっているのか皆の気持ちがバラバラになってしまい、どんよりした空気になってしまっている状態というのでしょうか。このまま練習を続けても意味がないなと判断した時に、その機会を見逃さず、ミーティングの時間を設け、話し合いをしてもらっています。
気持ちがまとまっていないまま練習をするより、何のためにという目的や目標、進むべき道が共有できた時、練習の質が変わるように思います。
また、日頃の練習には、朝練・放課後練・休日練があります。月曜日と木曜日の朝練は基本的に全団員が出ていますが、放課後練・休日練はコンクールの出場メンバーで集中して行っています。
この放課後練・休日練は、基本的に子どもたちにどのくらい練習したいか家のスケジュールをもちよって話し合ってもらい、自主的にスケジュールを組んで行っています。というのも、今の子どもたちは塾や習い事でとても忙しいですからね。
子どもたち同士で話し合い、練習日程を決め、それに対して何か気になったことがあれば私が助言をする、というようにしています。学校によって活動時間もさまざまです。本校では、6時間目まで授業があると、集まれるのが4時前くらいになってしまい、合わせて40分くらいしか練習量が取れません。
他校の合唱団に比べたら、とても少ない練習量だと思いますが、みんなそれぞれが忙しい中、工夫し、1分1秒の時間を大切に練習に取り組んでいます。

―練習の日程までも子どもたちで話し合って決めているとは驚きました。
思い返せば、八王子市立第一小学校合唱団の皆さんが、本番前に子どもたちだけで集まり話し合いをし、本番に向けて気持ちを高めている場面を目にしました。その際、鈴木先生はその様子を遠くから見守るというお姿がとても印象的でした。
今年のメンバーは、ちょっと暴走するくらいやる気に満ち溢れていましたね(笑)。でもそれが今回のこの結果に結びついたのだと思っています。
歌は、内面がそのまま出てしまうものだと思います。今日は何だか疲れているな、やる気があんまりないかな、というのは声を聴けばすぐにわかってしまうんですね。逆に、しっかり気持ちを作って声を出していると、本当に素晴らしい響きになります。
ですから、部活動の合唱指導の経験はほとんどない私ですが、子どもたちの様子をとても注意深く観察しながら、どのような声掛けをしたら良いだろうか、今どんな状態でどんな方向に導いたら良いか、探りながらやってきました。
―毎日とても少ない時間の中でさまざまな工夫をされて練習に取り組まれていらっしゃいますが、特に大切にされていることはありますか?
そうですね、今年からひとりひとりを見る個人チェックの時間を設けるようにしていることでしょうか。前任校の金管バンド部では常時部員は40~50名いましたが、それでもひとりひとりの個人チェックを必ずしていました。バンド指導でも合唱指導でも人数の多少に関わらず、小学校段階ではその重要性は同じだと思います。それ以外は、音取りC Dやタブレットを使用し、基本的にパートごとにリーダーを組んで練習に取り組んでいますね。
合唱をやる上で、まず大切なことは、正しく音を取れるようになるということだと思っています。どんなに一生懸命やっていても、音がはまらないといつまでも合唱の醍醐味であるハーモニーの美しさを味わうことができません。せっかく合唱をやっているのに、一生音楽の虜になってしまう魅力のあるハーモニーの美しさを味わえないなんてもったいない。だから改善できるようにできる限りサポートしています。
―個人チェックの時間を今年から取り入れたとのことですが、何か変化はありましたか?
はい。全体でなんとなく音を取っていた去年と比べて完成度が見違えるほど変わりましたね。ハーモニーの美しさを感じる瞬間が確実に増えました。
特に子どもたち自身から「今合っているね」とか「今は合っていなかったね」という発言が出るようになったことには驚きました。もちろん夢中になって気持ちよく歌うことも大事な時期ではあると思いますが、客観的な耳が育つと聴き方も変わってくることを感じています。
そうすると、音の高さを合わせることや、声の出し方を揃えることなど、より美しいハーモニーを作るために必要な気づきに繋がっていくと思います。
というのも、小学校高学年の思春期の時期は、耳もある程度育っているので自分の理想的な声で歌えないと、歌わなくなってしまったりと何かと難しい時期なんですよね。その時に何が原因なのかを認識できたら自ら改善することができるのではないかと思っています。
―ありがとうございます。
学校の部活としては他にもさまざまなコンクールがある中、この本協会主催、全日本こどもの歌コンクールに出場しようと思ってくださったきっかけは何だったのでしょうか?
そうですね、去年、まだ合唱団の運営が軌道に乗っていない時、その中でも特にやる気のある子たちが埋もれてしまっていたのがかわいそうだと思い、第2回のオンライン審査にソロで出てみたらどうだろうかと提案したのがきっかけです。2人のメンバーが出場し、1人は全国大会にも出させていただきました。
そこで出場した子たちが、参加してよかった、という感想を伝えてくれ、それだったら今年はみんなでチャレンジしてみようかと提案し募集をかけ、集まった5人でメンバーを組みました。
個人の技術が伸びることはもちろんですが、1人、2人が伸びるとその子たちが核となって全体のレベルを引き上げてくれます。個人のためでもありみんなのためにもなる、ひとりひとりの技術を伸ばすことはとても大事なことだと思っています。

―今回、アカペラでのご参加というのも大変魅力的でしたが、なぜアカペラの曲を選曲されたのでしょうか?
もちろん、ピアノ伴奏のある曲をとも思いました。しかし、5人という人数でしたので、ピアノとのバランスや声の響きが綺麗にハマった時の気持ちよさを、子どもたちに味わってほしいという私の想いもあり、アカペラの曲を選曲しました。アカペラ曲の中でもこの5人の個性やキャラクターなども考え、今回は「山男のヨーデル」にしました。
―小学校高学年になるとひとつの大きな壁として皆さん悩まれるのが変声期だと思います。合唱団を指導される中で、変声期の子どもたちとの向き合い方、ご指導について教えてください。
私自身も男なのでもちろん変声期を経験しています。歌えるバンドを目指していた小学生時代の吹奏楽部に入っていた時は、私もボーイソプラノとして高い声を担当していました。ですので、そこから変声期を迎える子どもの気持ちは実体験も踏まえて寄り添うことができると思っています。また合唱指導の先輩方の様々な素晴らしい実践があるのでそれを取り入れさせてもらっています。
例えば、私の恩師である田川先生からご指導いただいた実践のひとつに「おじさんクラブ」というものがあります。早めに声変わりする子は背が高かったり、体格がよかったり、顔も大人っぽくシュッとしてきます。しかし「お兄さんクラブ」のようにとかっこいい名前をつけてしまうとまだ変声期を迎えていない子がコンプレックスを持ってしまう可能性があるので、絶妙なラインでおじさんと呼びます。「いや、まだおじさんじゃないよ」と突っ込める冗談めかした言い方をしています。
大体低い「レ」の音が出せるようになると変声がだいぶ進んできている状態です。その低い「レ」の音が出る子たちは「おじさんクラブ」に入会となります。
変声の仕方も様々です。私は、3つのタイプがあると教えていただきました。
1つ目は、だんだん高い声から出なくなって低い声が出るようになっていくタイプです。これを「不便なおじさん」と呼びます。2つ目は、高い声も出せるまま低い声も出せるようになっていくタイプです。これを「便利なおじさん」と呼びます。3つ目は上の音も、下の音もしばらく出なく、苦しい思いをする時間が長いタイプです。このタイプはメンタル的にきついかもしれません。でもそのタイプも無理せずに歌っていれば低い声がみんなと同じようにいずれ出せるようになるので、絶対に大丈夫、焦らないでと伝えています。
この変声期というのは、早い子は小学校4年生から、ゆっくりな子は中学校3年生でも変声していない子もいるというように本当に個人差がすごいんですね。音楽の授業では、変声期に入り始めた子が多くなったクラスでは小学校でも混声合唱に取り組み、その子自身にどのパートが歌いやすいのか決めてもらって取り組んでもらうようにしています。出にくくなる音域も、タイミングも人それぞれなので、その子に応じて対応することが大切なのではないかと思います。
―とても面白い実践ですね。変声期はメンタル面等の心配もあり指導者の言葉掛けの重要さなど、とてもデリケートな問題と感じていましたが、「おじさんクラブ」の取り組みは成長を喜べる、そんな前向きな気持ちになれる方法ですね。
そうですね。「おじさん」と呼ばれるので、まだ変声期を迎えていない子もそこまで劣等感を持たずに、自分もいずれ経験することになる変声期について捉えてもらえるのかなと思っています。本当に難しい問題ですが、様々な先生方に教えていただいた実践を試し、日々悩みながら子どもたちと向き合っています。
―鈴木先生は音楽を通して、子どもたちにどのようなことを学んでほしいか、またそれをどのように将来に活かしてほしいと考えていらっしゃいますか?
そうですね。音楽を通して愛される人間になってほしいと願っています。中でも身につけてほしいなと思うことは礼儀作法です。
部活動では、これは歌に限らず楽器でも同じことだと思いますが、活動を通してたくさんの方々にお世話になる機会があります。その時に心から感謝の気持ちを周りに伝えられる人になってほしいと思っています。
さらに、音楽を楽しむことはもちろん、より一歩進んで音楽と関わりを持ってほしいとも思っています。ハーモニーの美しさを感じたり、ハモる楽しさを感じたり、その響きが気持ちいいと感じる耳を育てられたらと思っています。そして音楽を生涯にわたって楽しみ、音楽と共に生きていってくれたらと願っています。やはり、音楽で関わった子が今でも音楽を続けていると聞くと嬉しいですね。
今の教育界では教え込んではいけない、という風潮がありますが、大事なことは教える必要があると思っています。そしてそれは親や教師の役割だと考えます。
最初は何も知らなくて当然ですよね。物事の見方ひとつをとっても、ある視点が足りないなと思ったら、「こんな風な見方をしてみたらどう?」と問いかけ、子ども自身が様々な視点をもてるよう導く必要があると思っています。そうした教えを素直に受け取れる子は、そこから自身で気づけるように変わっていくものです。
学校では、教師同士の価値観が合わない場合、方針の違いで子どもが混乱してしまうことがよくありますが、幸い今の環境は同じような価値観で子どもたちを育てることができています。
―そうですね。音楽に限らず相手のことを想って行動できたら、先ほど先生がおっしゃっていましたが、結果的に愛される、応援される人間になれるような気がします。何もかも自分で気がつくなんてとてもできないことですし、そのように先生方に教えていただいたことってずっと大切に心に残りますよね。
私の尊敬する先生の言葉に「教えることを恐れるな」という格言があります。素晴らしい先生方はみんな仰います。「大事なことはきちんと教えてください、教えずに勝手に気づくなんて、そんな楽なことはないですよ」と。きちんと教えて、できたら褒めて、の繰り返しです。そしてできるようになったら手を離していけばいいんです。
でも、子どもたちからあまり尊敬されていなければその教えは「うるさいな」になってしまうんですよね(笑)。そこが指導者側の自分に突きつけられた、まだまだなところだと思っています。
私自身も子どもの時を振り返れば、いいなと思う先生の言葉は素直に聞きますし、ちょっと嫌いだなという先生に何か言われたらうるさいなと思っていましたから。とにかく、日々自分が勉強を続けるしかないと思います。
―八王子市立第一小学校合唱団の、今後の抱負をお聞かせください。
そうですね。可能性は無限にあると感じています。
現在赴任して2年目ですし、私自身合唱指導は不慣れなこともあるのですが、子どもたちの志気持ちに寄り添い、子どもたちの「やりたい」「やってみたい」気持ちをサポートしていけたらと思っています。
もちろん高学年になると、習い事や塾等でなかなか部活動に時間を割けなくなるという子もいるかもしれません。合唱団全体がちょっとセーブして楽しみたい、という雰囲気であればその路線でいくかもしれません。子どもたちのる気に応じてできるだけ柔軟に対応していきたいです。
今回このような賞をいただきましたこと、また合唱指導の経験がほとんどない私のインタビューということでとても恐れ多いですが、このような私の体験が、同じような境遇で苦しみ悩んでいらっしゃる方の参考となれば幸いです。

